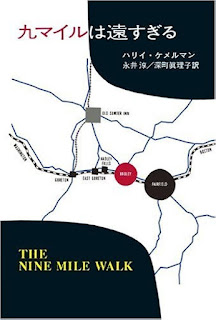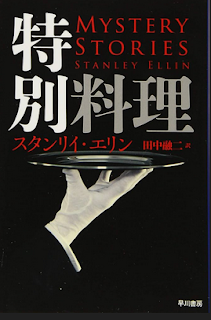リチャード・コンドン『影なき狙撃者』The Manchurian Candidate 1959
Richard Condon(1915-96)
佐和誠訳 ハヤカワミステリ文庫 2002.12
アメリカは革命中国を喪った。連続した朝鮮戦争は、新生中国を倒すための代理戦争の意味をも持たされた。朝鮮戦争が政治レベルの休戦交渉の段階に入った五一年、中国・北朝鮮側は、アメリカによって細菌兵器が使用されたと抗議した。さまざまの物証が呈示されたが、この件において、定説となるような確定事項はない。論者の立場によって、使ったとも使ってないとも主張される。朝鮮戦争史をあつかうあらゆる言説がそうであるように、水掛け論が
ここでも展開された。中国側は、捕虜にしたアメリカ兵士に罪状を告白させた。証言した兵士は祖国にもどってから証言には圧力があったことを明らかにする(当然これにたいしてアメリカ政府の圧力があったとするコメントも発生した)。ここで洗脳という言葉がにわかに脚光を浴びたのだった。用例の一つ――。洗脳されたアメリカ兵が「自分は細菌爆弾投下に従事した」と告白した。
これは共産主義の非人道性を攻撃する論拠になることが多い。シベリアに抑留された旧日本軍兵士が数年して故国に帰されたさいにも、同じ用語が使われた。洗脳とは、当初、共産主義思想を注入して個人の「思想改造」を試みることを指した。ナメクジ状生命体の寄生による脳コントロールというハインラインのイメージは、洗脳「される側」のおぞましさをよく表わしている。後に『人形つかい』は映画化されて、『ブレイン・スナッチャー』と改題された。脳に取り憑くのだから、こちらの語感のほうが近いだろう。
『影なき狙撃者』は、洗脳の諸影響をあつかった作品として(事実がどれほど取りこまれたかはさておいて)異色だ。ポリティカル・サスペンスとしてもかなり先駆的だろう。戦争で捕虜となった兵士が複雑なメカニズムの洗脳を施されてアメリカにもどってくる。スパイ小説におなじみのスリーパー・エージェントに近い存在。彼の脳にセットされた謀略を軸にストーリーは転がっていく。脳に施されたのは、正確には、後催眠だ。組みこまれた暗号がある配列を取ると、一定の指令として伝わる。しかし、あえて作者は、洗脳も催眠術も意識的に混同させて使っているように思える。
それだけなら怪しげな謀略小説に終わったところだ。『影なき狙撃者』の効用は、マッカーシーイズムについて、大胆な解釈を試みたところにある。赤狩りはしばしばジョゼフ・マッカーシー議員の個性に引きつけて語られすぎている。小説は、彼をモデルにした人物を登場させて、そこに二点のフィクションを加えた。一は、彼を大統領候補に仕立てたこと。二は、候補の妻(名前はエリノア。F・D・ルーズヴェルトのファースト・レディと同じだ)に隠れたコントローラーの役割を振ったこと。彼女はアメリカのビッグ・ママだ。彼は妻の意のままに操られていた、というわけだ。
マッカーシー的人物のほうが「操られた人形」だったとする解釈はスリリングだ。マッカーシー議員が用いたデマゴギーの低俗さや彼の個人的な性向の破廉恥さは名高いものだった。現実の上院議員は悪名を残した道化役だが、小説中の大統領候補は道化そのものだ。候補が暗殺のターゲットだと明らかになることによって、小説は別の深みを与えられた。兵士も候補も、ともにビッグ・ママの支配下にあることは疑いない。もしかすると、兵士が敵の洗脳にあっさりしてやられたのは、マザコンという決定的な弱みをかかえていたからではないか。いや、本当にそうだ。ところが標的になった候補はもともと妻に操られるだけの実体のない人物だった。
兵士は(もし仮に)洗脳から自由になったとしても、信心深いアメリカン・マザーからは自由になれないだろう。こうした確信をもたらせるところなど、『影なき狙撃者』という小説は、妙に「予言」にみちている。現職アメリカ大統領と彼のママ(二代前のファースト・レディだ)との結びつきの強さを連想させる。