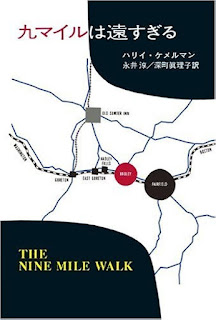ジム・トンプスン『内なる殺人者』 The Killer Inside Me 1952
Jim Thompson(1906-77)
村田勝彦訳 河出文庫 1990.11、2001.2
『おれの中の殺し屋』三川基好訳 扶桑社ミステリー文庫 2005.5
『現金に身体を張れ』1956でトンプスンのシナリオ協力をあおいだスタンリー・キューブリックなどは、彼のことを真正のバッドガイだと言っている。酒乱と粗野なふるまいは、創作世界のことだけではなかったのだろう。
『内なる殺人者』は悪徳警官ものの早い時期の作品だが、そこに分類されることは少ない。この主人公は、悪事そのものによってよりも、悪事をなす内面の痛烈さで輝く。サイコ・ミステリの先駆け的な傾向が、同時代に並んでいる。マーガレット・ミラー、ヘレン・マクロイ、パトリシア・ハイスミス、ジョン・フランクリン・バーディン……。とりわけトンプスンの特別な位置は、まるごとサイコ野郎の話だという点だ。
若い保安官補、見かけのナイスガイぶりを、間延びした愚鈍な南部なまりで隠しているが、そのもっと奥にはとんでもなく悪辣なサディストが潜んでいる。
これはまさに二十世紀なかばのアメリカ語で書かれた『地下生活者の手記』だ。だがこの男は知性のかけらも持たず、内省などとは無縁だ。他人を痛めつけることにためらいはみせない。彼のモノローグは、ヒーローの一人称でありながら、他のミステリのヒロイズムとは通じない。タフガイはタフガイのごとく語れというチャンドラー的戒律は、スピレーンによってすら守られていた。トンプスンにとっては、タフガイの本質は変質者だ。しかも彼はそのことを隠さない。彼の語る物語はサイコ野郎の自慢話でさえある。
彼が娼婦をぶちのめし、自らのキラーに目覚める場面は、最高に俗悪で、怖ろしい。現代の書き手のような丹念な残虐描写はむろん見られない。省略も多く、一定の検閲がはたらいてはいる。だが、ぶっきらぼうに積み重ねられる即物的な行動(殴る、蹴るなど)の平板さが、かえって息苦しさをもたらせる。特別の興奮もなく暴力を行使する男の内面〈インサイド〉は戦慄的だ。
その上、話者は、キラーは、殺人の一件を早く報告したくてたまらないのだ。犯罪者(とくに殺人者)の自己顕示欲は常人の理解を超えている、とよくいわれる。彼らが、自分の行為を悔いたり反省したりすることは遂にない。彼らは、他人がその行為の「崇高さ」を知るべきだと独り決めする。誇らずにおれないのだ。
行為そのものを語ろうと彼は焦る。《――心配するな、そのこと〈四字傍点〉もちゃんと話す。話したいんだ。起こったとおりのことをちゃんと》。これは、体裁通り読者に向かってのものではない。作者の「内なる殺人者」に向けての、文字通りの独白だ。
しっかり眼をあけて「俺の」行為を明瞭に理解しろ。と、俺のなかに響く声。作者が奏でる深遠なエコーが、読む者にも乗り移ってくる。
『内なる殺人者』と『死の接吻』を隔てるものは、このエコーの有無だ。三人の令嬢を狙った殺人者は、たんに計画性のない道徳的失格者に映る。彼の犯罪は現実の延長にあるので、彼への嫌悪をもまた常識的なレベルにとどまる。トンプスンの主人公は、良識の彼方にいる。